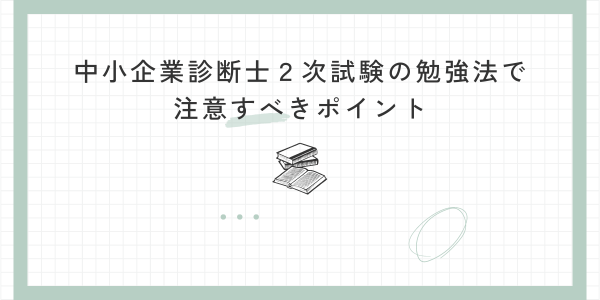中小企業診断士2次試験の勉強に取り組んでいる方、自分なりの勉強スタイルや回答の型は確立できたでしょうか?私は2次試験を合格して同期合格者と一緒に受験生支援をしているのですが、同期合格者と勉強方法について話をしていると「ん?」と気づいたことがありました。
このことを理解せずに、予備校や先輩診断士、Xなどでアドバイスを受けると合格が難しくなるかもしれません。
今回は、そんな同期合格者と勉強方法について話をしたときに気づいたことをお伝えしたいと思います。
二次試験攻略のコツとテクニック
二次試験は一次試験が終わってから約3か月で仕上げないといけないこと、更に試験内容は今まで経験してきた入試や簿記2級などの試験、一次試験とは打って変わって別物であり、かなりのハードモードです。実際、私も一次試験の自己採点で合格点に達していると分かった8月上旬の段階では、「一体何をしたらいいの?」と今までの試験対策とは全くの別物なことに絶望感を覚えていました。
ただ、二次試験に一発合格した今となっては、何をすればいいのか、何をしたらいけないのかが分かります。
その二次試験攻略のコツとテクニックを今回ご紹介します。
回答のヒントはすべて与件文の中にある
よくある失敗するパターンとして、勝手に事例企業を想像して想像で回答を書いてしまうパターンです。
いわゆるポエム回答というやつです。
中小企業診断士試験はあくまでの資格試験なので模範解答があり、それになるべく似た答えを書く必要があると思います。(公開されていないので定かではありませんが。)
であれば、回答に対するヒントは必ずどこかに書かれていなければおかしいのです。多くの受験生が受けているので、ロジカルに導き出せるようにしないといけないからですね。
なので、当たり前のことですが、回答は与件文から探しましょう。
とはいっても、ただ単に抜き出せば良いというわけではないので、注意が必要です。
与件文に書いてある通りの表現で書くのは当然のこととして(リスクを避けるため)、一次試験で勉強してきた知識を活用して回答を組み立てて行く必要があります。
設問で問われたことに対して答える
これもよく失敗するパターンです。設問で問われていることではないことを回答してしまうのです。そんなバカなことあるわけないと思うかもしれませんが、かなりの頻度で書いてあります。私は中小企業診断士受験生支援団体タキプロで勉強会を開催していますが、設問を全く無視して好き勝手書いている回答を何度も見てきました。
これは特に多年度生に多い特徴です。シンプルに設問に回答していないので得点が取れず落ちているわけですね。
なので、設問をよく読んで、何を問われているのかを明確にしてから回答の組み立てを始めてみてください。
シンプルなロジックで読みやすい日本語で書く
これもまあまあ多いです。100字や150字を埋めるためにキーワードを詰め込んだり、接続語でつなげたりした結果、何がいいたいのか分からない文章になっているのです。
これは文章センスのある方は最初から綺麗で読みやすいのですが、読みづらい文章を書いている人は何度アドバイスをしても直らないケースがあります。
これも多年度生に多い特徴の1つですね。何が言いたいのか分からないので採点者もおそらく大して読まずに得点をつけるのでしょう。ライバルがいる土俵にすら乗れていないのではないでしょうか。
ですので、シンプルに書きましょう。コツは一文をなるべく短く書くことと、言いたいことは一文に一つまでと決めることです。
三段論法が分かりやすいですね。A=B。B=C。よってB=Cである。といった具合です。
まあ、診断士試験ではこのようなロジックはあまり使いませんが、それぐらいシンプルで良いということです。
回答パターンをあらかじめ用意しておく
これは私が実際にやっていた方法で、個人的には診断士試験に合格する王道パターンだと思っています。例えば、先ほども出たタキプロ内で勉強会を開催した際、同期の合格者と話をしていると多くの人が回答パターンを確立していて、当日はキーワードを当てはめるだけにしていたと言っていました。
これを聞いて私は自分のやり方が正しかったのだと納得しました。
初めて二次試験を受ける人は分からないかもしれませんが、二次試験は本当に時間が足りません。過去問では体験することのない緊張感の中、初めての与件文を読み、内容を理解し、回答に答えていく。しかも、100字だったり150字だったりと文章を組み立てないといけないわけです。
一から文章を組み立てていては到底時間が足りず、おそらく半分も回答できないのではないでしょうか。
なので、あらかじめ回答のパターンを決めておくのです。
これは人のよってまちまちですが、私の場合は、人事施策について聞かれたら〇〇と答えよう、プロモーション活動について聞かれたら〇〇や△△と回答しようとおおよその方向性を決めていました。
当日は設問を見て、それに見合ったキーワードを与件文から探し出すといった作業のみです。過去問を5年分くらいやれば、どんな問題が出てくるのか傾向が掴めるはずです。そして模範解答を見ればどういった方向性の回答を書いているのか分かりますので、それらをまとめて分析します。
そうすると、この試験が何を回答してほしいのかがなんとなくわかるようになります。
こうしたプロセスを経て、自分なりの回答の型が完成したら8割くらいは合格と思ってよいのではないかと思います。それくらい差がつきやすいポイントだと思います。
エゴを出すな
最後のコツというかポイントは、「エゴを出さないで書く」というものです。今まで書いてきたことと似ているのですが、この心持ちで試験に臨んでいるのと臨んでいないのとでは雲泥の差です。コンサルタントというと、自分なりのロジックで誰も思いつかないようなウルトラCを提供するものだとイメージする方もいるかと思いますが、そうではないです。
多くの人が知っていることだけれど、着手できていないことを着実に現実的な施策に落とし込んでシンプルに実行支援していくわけですね。特に診断士試験においては、自分の色を出そうとか誰も思いつかないような回答が思い浮かんだと回答しては、おそらく得点は期待できないのではないでしょうか。二次試験はあくまでも相対評価なわけですから、多くの受験生が思いついていることを当たり前に書いていくことで得点を積み重ねていくイメージです。それぞれの戦略によりますが、80点を目指すのではなく上位2割に入る回答を書くイメージです。60点未満を取らないようにする、といった方が分かりやすいですかね。
一点一点の積み重ねが合否を分けるので、確実に合格できるように慎重に得点を積んでいく練習をしていきましょう。
二次試験の勉強法でやってはいけないこと
二次試験の勉強をする際にやってはいけないこともあります。これらをやっている人は今すぐ見なおしてみましょう。
多くの問題集やYouTubeを見る
これをやってしまって迷走している人は少なくないのではないでしょうか。
今や検索すればたくさんの情報が出てきますね。XやYouTubeなど最たる例で、たくさんの人が診断士試験に合格するにはこうしたほうがいい、この勉強をしておきなさい、とアドバイスしています。かくゆう私もそうですね。
一次試験に通ってから3か月しかないわけですので、素早く情報収集して、この勉強法で行くのだと覚悟を決めましょう。
模試で一喜一憂する
多年度生に多いです。模試を何社も受けて、〇〇社の模試はA判定だったからよかった、〇〇社はD判定だったから絶望しかない、などと模試の結果で一喜一憂しているのです。
私は模試を受けていないのですが、そもそも模試は受ける必要などないと考えています。(あくまでも私個人の意見です。)
なぜなら、模試と二次試験は全くの別物だからです。
模試でよかったからといって本番で合格するとは限りませんし、逆も然りですね。
模試を受けるとなると一日費やすわけですから、個人的にはかなりもったいないことだと思っています。その時間があれば家で過去問を分析して、ロジックパターンを組み立てるのに使った方が何倍も有意義だと思います。
模試を受けるメリットはただ一つ。本番の時間配分に慣れるためだけだと思います。
私も二次試験の時間配分は苦労したのですが、この有効な対策が一つあります。
それは「過去問を60分で解くこと」です。これもタキプロの合格者仲間が同じことを言っていたのでかなり有効性のある対策だと思います。
理由としては、本番は、自宅で過去問を解くよりも圧倒的に緊張していることや、初見の問題なので何度も読み返すだろうと想定していたからです。(案の定、事例Ⅰは緊張で最初の10分くらいは全く与件文が頭に入ってきませんでした。)
そして、過去問も80分想定で解いていては本番では絶対に80分では解ききれないと思ったからです。
なので、過去問演習の際は、60分で解ききるようにしました。もちろん、最初は2時間かかっても回答を書けずにフリーズしていましたが、何度も繰り返すうちに60分以内で解けるようになります。問題や回答を多少覚えているというのもありますが、それでも「〇〇と問われたら〇〇と回答する」というロジックが頭に定着している確認になり、当日も素早く対応できるようになるのです。
私は、過去問は6年分を3周しましたが、3周目は40分くらいで回答できていたので、本番では5~10分程度余裕をもって終わらせることができました。
マーカーで線を引くことに集中する
これも多年度生に多いです。マーカーを4~5色持ってSWOTで色分けして引いている人ですね。この方法で合格している人もいるので間違いだとは言えませんが、マーカーで線を引く時間がもったいなくないのかな?とシンプルに思います。
私は、マーカー一色で使えそうなキーワードや重要なポイントに線を引くのみでした。
一回与件文を読めば大体のストーリーはつかめるので、あとは設問に応じて与件文からそれらしいキーワードを探していくといった感じでOKです。
マーカーを何色も使っている人で時間が足りない人はそのやり方を見直してみてはどうでしょうか。
インプット中心の勉強法をやっている
二次試験は一次試験とは違い、文章で書いていく試験です。なので、圧倒的にアウトプットが必要です。テキストを読めばなんとなく回答できる一次試験とは別物です。
最初は模範解答の模写でいいので、手で覚えこませるイメージでとにかく書いていくことで、何を書けばいいのか、何が重要なのか、が分かっています。
二次試験において、テキストのインプットだけでは合格はかなり遠いのではないでしょうか。
過去問を解いた後の振り返りをしない
過去問の振り返りをしないのもよくないです。そもそも診断士とは何ぞや?ということなのですが、診断士の仕事こそPDCAを回していくことだと思います。
計画を立てて、やってみる、見直し改善して、またやってみる、この繰り返しで中小企業の経営を助けていくわけです。であれば、自分自身の振り返りを当然するべきですよね。
過去問を解きっぱなしにするのではなく、自分の回答のクセと間違いやすいポイント、回答できている得意なところなどを分析して、次の過去問で改善していくのです。
中小企業診断士二次試験の勉強法で注意すべきポイントのまとめ
今回は二次試験の勉強法で注意すべきポイントを上げました。
具体的な方法ではなく、抽象的な心構え的な話が多かったと思いますが、中小企業診断士受験生支援団体タキプロで受験アドバイスをしてきたからこそ、今回あげたポイントをやっている人とやっていない人の回答のクオリティの差があまりにも激しいので書くことにしました。
特に「設問にシンプルに分かりやすい日本語で回答する」というのは重要です。合格する人の回答はとにかく読みやすい、分かりやすいです。
一回読んで何が言いたいのか分かります。多年度生で何度も落ちている人は読みにくいので、3~4回読んで「こういうことかな?」と本人に「これってこういうことだよね?」と確認することが多いです。その差は本当に大きいです。
なぜなら採点者は何百人と回答を読まなければならないからですね。
一度で理解できない回答の得点が高いとは私は思えません。そういった意味でもとにかく読みやすい回答を書くことを心がけていただければ良い結果につながるのではないでしょうか。