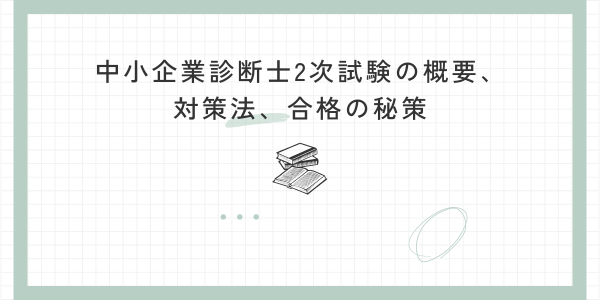中小企業診断士の2次筆記試験は診断士になるための最も大きな壁であると同時に、理論的な知識だけでなく、実務的な応用力や問題解決能力が求められますので、診断士の面白さを感じ取れる試験でもあります。
私は、1次試験は2回受験しましたが2次試験は1回でクリアしたので、今回初めて2次試験を受験する方であっても1次試験の合格が分かってから勉強しても十分間に合いますので安心してください。
試験の形式や内容を理解し、効果的な勉強方法を実践することで、自信を持って試験に臨むことができます。
この記事では、2次試験の概要から、試験対策の具体的な方法、試験当日の準備までを詳しく解説します。
中小企業診断士二次試験の概要
二次試験は「人事・組織」「マーケティング」「生産管理」「財務会計」の4事例が出題され、1題につき80分間の論述式試験です。
ただ単に、知識が問われるだけでなく、中小企業診断士として事例企業にあった施策を助言する必要があるため、与件文と設問文をしっかりと読み込み理解することが重要になります。
二次筆記試験の効果的な学習法
私が試験勉強中に行った方法は、以下の通りです。
- 過去問を解く
- ふぞろいな合格答案で採点する
- 問題のパターンやよく聞かれる内容、回答フレーズをまとめる
- 二次試験合格者の頭の中にあった全知識、全ノウハウで必要な知識を補う
- 過去問を繰り返す
それぞれを詳しく解説します。
過去問を解く
まずは中小企業庁の公式サイトや受験予備校のWEBサイトで過去問をダウンロードします。
このとき、私は必ず紙に印刷していました。
理由は、本番も紙の問題と答案用紙だからです。
普段から本番当日と同じ環境で勉強することが資格試験では重要だと考えています。
できるだけ本番を想定して対策することで余計な気を遣わずに済みます。もちろん、iPadなどのタブレットやスマートフォンで勉強する方が効率良いという方はその方法でも構いません。
さて、過去問をまずはどの年でもよいので一度通して解いてみましょう。制限時間は80分です。おそらく最初は全く解けない(書けない)と思います。特に事例Ⅲ。
私はR4の事例Ⅲを初めて解いたときは6点でした(ふぞろい採点)
80分を超えて2時間粘りましたが、全く解けずギブアップして模範解答を確認しました。
この解けなかった経験があるからこそ、今から始める勉強によって成長していることを実感し3か月間の二次試験勉強を頑張ることができるのです。
ふぞろいな合格答案で採点する
中小企業診断士二次試験は解答が出ません。よって、何を書けばいいのか、何が得点に結びつくのかが曖昧で、これが二次試験の難解さの原因になっています。
ただ、これは診断士になった今では当たり前のことだと思います。
というのも、中小企業の経営診断や経営アドバイスにおいては明確な答えがないからです。
対象企業の持っているリソースの中で、出来うる施策を地道に実行支援していき、出来ていないことを改善して、また実行するというPDCAを回していく他ないからです。
ただし、資格試験である以上は何かしらの得点の基準というものがないと採点の軸がぶれると考えられるため、おそらく模範解答(非公開)を用意しているのではないかと思います。
ここからがこの章のポイントです。
利用するのは、二次試験を受験する受験生のほとんどが利用しているであろう神教材が「ふぞろいな採点答案」(以下、ふぞろい)です。
何に何点入っているのか目安を知るためにはこの教材しかありません。
ふぞろいは、前年度の診断士二次試験を受験した人を対象に、再現答案を募集して、回答と得点(事例の合計点)からキーワードごとに得点の目安を示してくれています。
私の感覚ではほぼブレがなく、かなり精緻なデータであると感じています。(これをまとめるのは相当大変だと思います。)
このふぞろいを利用して、自分の答案の自己採点をしていきましょう。
ポイントは、「解説をよく読むこと」と「点数の高いキーワードを覚えること」です。
どういう考え方が必要なのか、また高得点になっているキーワードや回答方法はどういったものなのかをひとつずつ覚えていきます。
かなり地味な作業ですが、こういう地味な作業が1か月半くらい経つと効いてきます。
問題のパターンやよく聞かれる内容、回答フレーズをまとめる
私はとりあえず2年分(R4、R3)の8事例を解きましたが、合格点を満たしているものはありませんでした。
この記事を読んでいる人たちも「こんな点数で大丈夫なのか?あと2か月しかない」などと不安になり焦りを感じているかもしれませんが、大丈夫です。十分間に合います。
私の場合はここで少し寄り道をしました。
この寄り道が安定的に60点以上を取るための秘策といっても過言ではありません。
2~3年分の過去問をやれば、各事例で何を問われているのか、設問のクセやパターンに傾向があることが分かってきます。ここで過去問から離れて、ふぞろいで問題パターンや高得点キーワードなど「こう聞かれたらこう答える」といった回答集を作成していきます。
具体的には、別記事で書こうと思いますが、例えば事例Ⅰなら「さちのひもけぶかいねこ」という有名なフレームワークがありますが、それぞれに施策とメリット・デメリットをまとめて一覧表にしていきます。
施策はふぞろいや全知識全ノウハウから抜き出していきます。メリット・デメリットも同じように全知識などに書いてあるので、抜き出していきます。
正直、この作業をやっている間は「こんなことをやって意味があるのか?」「過去問をどんどんやるべきではないのか?」と不安が襲ってきますが問題ないです。
この施策とメリット・デメリットをまとめる作業こそ超重要ポイントです。
こうして一つずつ自分でまとめていくことにより、自然と回答を組み立てる基礎力が身に付き、過去問を見た瞬間に書くべき施策が思いつくようになります。人事施策について聞かれたら「新卒採用、中途採用、インターンシップ、非正規社員登用」など3~4個の施策がパッと頭に出てくるので、それをあらかじめ用意しておいた回答の型に当てはめるだけです。
ちなみに、まとめるときに注意してほしいのですが、あくまであなたが試験当日に思いつく内容やフレーズであることが大事です。全知全能やふぞろいを読んでいるとカッコいいフレーズや小難しそうな言い回しがありますが、自分に合わないフレーズは使わないことです。自分のモノに出来ていることが何より重要です。
2次試験合格者の頭に合った全知識、全ノウハウで必要な知識を補う
上記の通り、全知識、全ノウハウで必要な知識をインプットします。
ここで大事なことは「試験中に自分が思い出すことができる内容」であることです。
例えば、私の場合で言えば、マスカスタマイゼーションという言葉がありますが、「なんとなくこういうことだよね?」とふわっとした雰囲気は分かりますが、十分に理解できていなかったため、回答集には入れませんでした。
こんな感じで自分だけの回答集を作っておくと、とても楽になります。
過去問を繰り返す
回答集が作れたら、二次試験に対応できる知識は身についているので、過去問をひたすら時間の許す限り解いていくだけです。
おそらく、初見でも60点前後はとれるのではないでしょうか。
ここからは細かいフレーズや文章の綺麗さなどを追求しながら、回答集をブラッシュアップしていきましょう。
過去問の模範解答で良い言い回しやフレーズがあればどんどん採用していきましょう。(あくまで自分が試験当日に書けそうなものですよ。)この回答集はファイナルペーパーといって試験当日に見直す重要な役割を担います。
二次試験合格の鍵は自分の型を確立できるかどうか
二次試験は公式解答がなく、何に何点入ったかわからないため、「この勉強法が絶対的に正しい」というものがありません。
私を含め多くの先輩診断士や予備校が二次試験対策の情報を発信していますが、どの方法も正しくもあり、間違っているのかもしれません。大事なことは自分に合いそうな方法を試してみて、しっくりくればその方法を継続してやりながら自分流のアレンジしていくことです。
PDCAを回していくってことですね。
例えば、私は4色マーカーでSWOTに合わせて線を引くという方法を複数の方からおすすめをされたので、最初はしていましたが、ペンの持ち換えに時間がかかる上に、線を引くことに集中してしまい与件文が頭に入ってきませんでした。また、与件文がごちゃごちゃになって汚くなるのも嫌だったので、3回くらい試した後、スパっと辞めました。(この3回の間にも試行錯誤はしましたが。)
結局、ライトグリーンのマーカー1本で与件文のキーワードや気になる記述をマークするという手法に変えたため、与件文の読み込みスピードは2倍以上に上がりました。
このように自分なりの回答スタイルを確立していくことが大切だと感じます。
そして、この回答スタイル(=型)を身につけた人はかなり合格に近いのではないかと思います。
おそらく、YouTubeやX、ブログ、先輩診断士など色々な人から勝手にアドバイスされ、迷うこともあると思いますが、先輩に勧められたからといって、合わないのに継続してやる必要はありません。
過去問をやりこみ、自分なりの型を見つけ、二次筆記試験を突破できることをお祈りいたします。